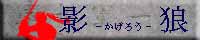
二話
――夕暮れ とある武家屋敷
屋敷の奥まった一室に、人の気配があった。
燈台の揺らめく明かりに照らされた薄暗い室内。簡素ではあるが、堅牢な作りの調度品。
その中に漂う、濃密な牡と牝の匂い。
そして、血の臭い……
一糸纏わぬ男女が絡み合っている。
一人は三十代半ばの女。切れ長の瞳。やや厚い唇。豊満な胸と腰に、引き締まった腰回り。妖艶な雰囲気を持つ女だ。
そしてもう一人は、まだどことなくあどけなさを残す顔立ちの青年。あの、影――戌彦――だ。端正な顔立ちに、細身だが、筋肉質で引き締まった身体。体中
に刻み込まれた無数の傷跡。そして、右肩の刺青。図形を組み合わせた様な、奇妙な模様だ。
「…………」
声にならぬ、喘ぎ。
女が戌彦の身体を舌で愛撫している。
その舌は、あたかも蛞蝓の如く蠢き、青年を責める。首筋。胸。脇腹。
戌彦の顔は上気し、その眼は欲情に曇る。
その手は女の豊かな乳房を弄んでいた。
「ふふ……いいよ、あんたの身体に染み付いた血の匂い……。それだけであたしのココも、潤んでくるよ」
紅い唇が妖しく踊る。
戌彦の手をそっと己の股間に導く。そこは、既に潤みを帯びていた。
「ふん? ココまで……」
「……っ!」
一瞬怪訝な顔をすると、女は戌彦のいきり立ったモノに舌を這わす。
――ぴちゃ……ぴちゃ……
いやらしい音が響いた。
先端、裏側……執拗に舌が絡み、責め立てる。
「ふふ……感じるかい?」
「……」
「みたいだね。……ところであんた、あの娘を犯ったね?」
「!」
戌彦は身体を強張らせた。
「ふふ……破瓜の血とあんたの子種、若い女の蜜。あたしの鼻をナメちゃいけないよ」
女はニヤリと笑った。あたかもそれは、女狐の笑み。
「そう言う奴には……こうよ」
言うや否や、女は少年のモノを喉の奥まで飲み込む。
「……ぁっ!」
――びくん
戌彦の身体が震えた。
苦悶とも、喜悦ともつかぬ声。
――じゅぶ、じゅぶ……
女の口は彼のモノを包み込み、絶妙な舌使いで貪った。
「……」
戌彦は思わず身体をよじる。熱いモノが下腹部にたぎり、最早爆発寸前だ。
「ふふ……イくのかい? なら、遠慮無く出しな!」
女は口を放すと、手でしごき始める。
「……っ! ……」
戌彦は快感に飲まれ、愉悦に顔を歪めた。
「ふふ……可愛いよ、その顔。どうだい? もう出るかい?」
女はそれをきつく握り締め、先端を舌で抉る。
「――――!」
その瞬間、戌彦のそれから、熱いモノが迸った……。
「……ァ、ハァ……」
戌彦は、ぐったりとしたまま荒い息をつく。
その前に、女が腰を下ろした。
彼の顔の前に、女の秘部がくる。
「さあ、お舐め。犬みたいにね……」
彼女は唇の周りに付いた白い粘液を舐めると、戌彦に命じた。
「……」
彼はその前に跪くと、秘裂に舌を這わした。
深い叢に覆われた、肉色の秘裂。じっとりと蜜で濡れたそこは、舌が触れる度に物欲し気に蠢いた。
「ン……くっ! ふぅ……いいよ。陰所(ほと)を、もっと奥まで……」
女は上気した顔で、喘ぐ。
――ぴちゃぴちゃ、ちゅぷちゅぷ……
淫らな水音。
「あっ……ナカも……」
その言葉に応じ、戌彦は右手の指を二本軽く舐めると女の秘裂に挿入した。
「ンぅっ!」
女の身体がのげ反り、豊かな胸が淫らに波打つ。
戌彦の指が、激しく女の中を掻き回す。そして、その舌が、肉芽を抉る。そして、左手の人差し指で、後ろのすぼまりを撫でていた。
「はぁっ、あっ、いいよ、ソコ……もっと、激しく……ああっ!」
がくがくと腰が揺れる。
戌彦はそれに応じる様に、更に激しく責める。指を鍵の様に曲げて壁をこすり、すぼまりに指を突き入れる。そして、肉芽に歯を立てた。
その瞬間、飛沫が戌彦の顔を濡らす。
「あ〜〜〜〜!!」
女の白い喉がのげ反り、大きく身体が打ち震えた後、がくりと頽れた。
「良かったよ……入れたいかい?」
女は欲情に潤んだ瞳で、戌彦の股間のモノを見つめた。それは既に再び起立し、びくびくと脈打っていた。
戌彦は無言で頷く。
「じゃあ、おいで……」
女は脚を広げると、自ら花弁を開いて見せる。
――ぐちゅ……
淫らな音を響かせ、女のそこは、戌彦のそれを飲み込んで行く。
「ン……いいよ、そのまま奥まで」
「……ぁぁ」
戌彦はそこの熱さに喘いだ。
女のそこは熱く、優しく彼を包み込んだ。それでいて、決して逃がさぬ様にしっかりとくわえ込んでいる。
「どうだい? 母娘とはいえ、だいぶ違うだろう? 若い娘のは良かったかい? ……でも、あたしも捨てたモンじゃないだろう?」
「……」
こくりと頷くと、戌彦はゆっくりと抽挿を開始した。それに応じ、蠢く襞が彼を絡め、貪る。
――ぬちゅ……くちゅ……
淫音を響かせ、二人の腰がぶつかり合う。
女は戌彦の首に腕を絡め、抱き寄せた。
舌を絡め、お互いを貪る。
暫し後、唇が離れた。
つ……と唾が糸を引き、切れた。
女はそっと彼の両頬に手を当て、見つめた。
「ふふ……ずいぶんと信顕(のぶあき)様に似てきたわね。初めて会った頃のあの方に、瓜二つ……」
女は悲し気に微笑み、再び唇を重ねた。
戌彦は彼女の背に腕を回し、抱き締めた。
「し……ま、かあ、さま」
くぐもった声。かつて負った心の傷が、言葉を奪っていったのだ。
「今は、志摩と呼んで……」
耳元での、優しい囁き。その傷を癒す様な……
「しま……」
こくりと頷くと、戌彦は彼女を見つめた。
「だから、もっと強く……」
戌彦は彼女の足を抱えて組み敷く。そして、腰の動きを加速する。
「あっ……あぅっ!」
たまらず志摩は嬌声を上げる。
「強く! 痛いくらいに……」
それに応じ、彼女の胸を揉みしだく。戌彦の手の中で柔らかい肉塊は、いやらしく姿を変えていく。戌彦はその先端を口に含んだ。
「あっ……いいよ、ソコ……あうっ!?」
甘噛み。
志摩の身体が一瞬硬直し、脱力した。
「!」
強烈な締め付けが、戌彦を襲う。が、彼は大きく息を吐き、かろうじてその快感をやり過ごした。
一瞬の間を置き、再び腰を打ち付け始める。
「あふっ!? ……あぁっ!」
志摩はたまらず悲鳴を上げる。敏感になっている所を更に蹂躙されたのだ。
「ま……待って。このままじゃ、またすぐに……」
彼女は荒い息をつきながら、戌彦から離れる。
「……こんどは、あたしが上よ」
仰向けになった戌彦のものを手で擦りつつ、再び花弁に宛てがう。
「……」
「早く入れたいかい? でも、駄目」
焦らす様にゆっくりと腰を下ろしていく。
「さっきはいかされたからね……だから、まだよ」
先端をくわえこんだ所で一度腰を止めた。
「うっ…………」
戌彦が呻いた。快感を求めて腰を突き上げようとする。が、志摩は巧みにそれをいなす。
ゆっくり……ゆっくりと、戌彦のモノが志摩の女陰に埋まっていく。
「ふふ……じっくり楽しまないとね」
戌彦にとっては気の遠くなる様な時間の後、彼のモノは、志摩の中に飲み込まれた。
「ふぅ……いいよ。もっと、楽しませて。あんな男の事、忘れるぐらいに……」
その目尻に微かに涙が光っている様に見えた。
「……」
戌彦はその彼女をぐい、と突き上げる。
「あっ……」
志摩は嬌声を上げると、自らも腰を振る。
ぐちゅ、ぐちゅ……といやらしい水音が結合部から響く。
抜ける寸前まで腰を上げ、次いでゆっくりと根元まで飲み込む。
また、腰を大きく回す様に振り、戌彦のモノを貪っていく。
「……っく」
戌彦は、思わず呻きを漏らす。
「どう? そろそろいきそうかい?」
志摩は腰の動きを加速する。
戌彦も腰を突き上げる。次いで、手が胸に伸びた。下からすくい上げ、乳首を摘み、指先で転がす。
「いいよ、もっと、もっと強くっ!」
嬌声が高まる。
戌彦は一際大きく腰を突き上げ、乳首を強く捻り上げた。
「あ〜〜〜っ!」
志摩は白い喉を反らせて髪を振り乱し、果てた。
同時に痛いほどの締め付けが戌彦を襲い、たまらず彼も熱い滾りを彼女のなかにはなっていた。
「信顕様……」
がくりと頽れた志摩の唇から、再びその名が漏れた。そして、その瞳には、涙が浮かんでいた……
彼女の首を抱きつつ、戌彦の意識は暗闇の中に落ちていった……
――しゅる……
戌彦は微かな衣擦れの音に、目を覚ました。
裸で寝ていた彼に、布団が掛けられている。
その彼が見上げた先で、志摩は見繕いをしている。着物を纏い、髪を整える。
その姿は、貞淑な武家の妻だ。先刻の妖艶な女の面影など、微塵も無い。
「戌彦……暫くは、ここにいなさい。まだ、部屋に戻っては駄目」
優し気な、気遣う声。あたかも、慈母の様な……
そして、身を起こした戌彦を抱き締める。
「かあさま……」
彼もぎこちなく、彼女を抱き寄せた。
「戌彦、いや信祐(のぶすけ)様……。もうすぐ、もうすぐです。お父上の無念を晴らし、御家を再興する為に、妾は……」
「…………」
半ば狂気に染まった彼女の瞳に見つめられ、戌彦は無言であった。
「大丈夫……全てあたしに任せて。全て、上手く行く……」
女の顔。母の顔。妻の顔……
彼女の顔が、めまぐるしく変わる。
戸惑いと哀しみが、戌彦の顔をよぎった。
「さて、と……そろそろ行かないと。あの男の通夜の準備もあるしね」
それに気付いたのか、気付かなかったのか……
彼女は戌彦から離れ、立ち上がる。
「それに……あの娘を慰めてやらないとね……」
部屋から出る直前、その顔に浮かんだのは女狐の様な笑みであった……
「はは、うえ……」
戌彦はその後ろ姿を目で追いつつ、一人呟く。
「おれ、は……どうすれば良い……」
拳をきつく握りしめる。
「……あや……め……」
戌彦は、自らが汚した少女の名を呟いた……