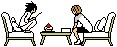
ケーキ
|
「ねえねえライト君、ケーキ買いに行かない? すっごく美味しいって評判のお店があるのよ」 大学の授業を終えて、家に帰ろうと準備をしているとパタパタ靴音を響かせながらクラスメートの女の子が駆け寄ってきて、そう言った。 たまたま通りがかった竜崎の脚の動きが、ピタリと止まる。 ・・・こういう意外にも食い意地が張っているところは、リュークによく似ている。 竜崎は、僕とは違って他人との関わりを避けたがる傾向があるから、このときも会話に参加しようとはしなかった。 それでも、ケーキという単語には、いちいち反応を示しているところをみると、よほど食べたい気持ちになっているのだろう。 グルメだと自負している女学生が、そのケーキの素晴らしさを語ってみせるものだから、甘党の竜崎にしてみれば、たまらないんだろうな。 会話に参加したいくせに、他人とは距離をおいておきたいという気持ちが強くて葛藤している姿は、ちょっとだけ可愛くて、つい情にほだされてしまったんだ。 「流河、一緒にケーキ買いに行かないか?」 僕とは大学内でも【友達】で通っているから、僕の誘いにならついてきたって不自然ではない。 そのときの竜崎の顔ったら、まるで小さい子どもみたいに無邪気で、心の底から嬉しそうだった。 ケーキ屋のショーケースの中に並べられている商品を見つめる横顔も、リンゴを見つめるリュークの様子にどことなく似ていて落ち着きがない。 迷った末に竜崎が選んだのは、苺タルトと苺ショートだった。 僕はチョコレートケーキを3つ注文した。そのうち2つは母と妹の分だ。父は仕事が忙しくて今日は帰ってこない。 買い物を済ませた後、なんとなく視線を感じて振り向くと、なぜか竜崎と目が合った。 いつもなら竜崎は自分の用件が済むと、すぐに高級車に乗って帰っていくんだけど、今日はケーキ箱を大事そうに抱きかかえたまま、時折、何か物言いたげにチラチラと僕に視線を送ってくる。 クククッとリュークがおかしそうに笑った。 『ライト、あいつ早くケーキが食べたいんだぞ、きっと』 言われてみれば、車で自室に帰るよりも僕の家への距離のほうが短かいのだけれど・・・。 「流河、よかったら僕の家に遊びにこないか? たまには男同士で過ごすのもいいし。勉強も教えあえるから」 あんまり、いじましいので。つい、そう声をかけてしまう。男同士で、と付け加えたのは女学生がついてくるのを防ぐためだ。 僕の言葉を受けて、竜崎はまた、嬉しそうに微笑った。どうやらリュークの言うとおり、一分一秒でも早く食べたがっていたらしい。 そのまま竜崎をつれて家に着くと、ちょうど出かけようとしていた母とバッタリ鉢合わせしてしまった。 「僕の友達の流河だよ。ケーキでも一緒に食べようかと思って。母さんたちの分は冷蔵庫に入れておくから」 ケーキの箱を見せながら言うと、少しだけ嬉しそうな顔をしてから母は、すぐに眉を曇らせる。 「残念だわ。紅茶の葉も珈琲の豆も切れていて、今から買いに行くところなのよ。だから飲み物は麦茶しかないんだけど・・・」 ケーキに麦茶か。合わないけど、しょうがないな。 「構わないよ。じゃ、気をつけて」 母を笑顔で見送って、竜崎には僕の後ろをついてくるように促す。今日はケーキを食べるだけで帰ってもらう予定だから、キッチンに案内すればいい。 竜崎をテーブルにつかせ、すぐ近くの冷蔵庫にケーキ2個をしまって代わりに麦茶を取り出す。 そのままテーブルに戻ると、僕が座るはずの位置に苺タルトが置かれていた。竜崎の前には苺ショートが置かれている。 ・・・嫌味だろうか? 実は、竜崎とケーキを食べるのはこれが初めてではなかった。数日前のことが脳裏に蘇る。 その日、僕は甘党の竜崎のためにショートケーキとエクレアを土産に持っていっていた。2人で優雅にティータイムを楽しんでいると、突然リュークがショートケーキの苺を指差して 『ライト!リンゴみたいに綺麗な赤色の果物だな。俺、食べてみたい!!』 と騒ぎ出したんだ。死神はリンゴしか食べないって言ってたくせに。 運の悪いことに、竜崎が自分の分として選んだのもショートケーキだったから、僕の分として残ったのはエクレアだ。苺は乗っていない。 心の中だけで、我慢しろ!と一喝してやったが、リュークは諦めきれないらしくグルグルと僕と竜崎の周りを物欲しそうにうろつく。 竜崎も、さっさと食べてしまえばいいものを、どういうわけか苺を残してスポンジばかり嬉しそうに口にしているから、余計にリュークが騒ぐんだ。 このままでは我慢の限界を超えたリュークが勝手に、竜崎の目の前で苺に手を出しかねない。 しかたない・・・。どうも、竜崎は苺はあまり好きじゃなさそうだし。このケーキは僕が持ってきたものだから、いいよな? 自分で自分を納得させると、僕は竜崎のケーキ皿から、ポツンと残されている苺にフォークをさすと、さりげなくリュークに目配せをする。 僕の意図を読んで、リュークが喜び勇んで僕の背後へと飛んできた。 椅子に座ったまま上体を捻って後ろを向いて、竜崎の視界から僕の背中に隠されて見えなくなった苺をリュークに与えようとした・・・が。 鼻先まで顔を苺に近づけたリュークが、当然ながらリンゴとは違う香りを嗅いだとたん、嫌そうに顔を引く。 『ごめんライト。やっぱり喰えない』 だったら騒ぐなよ、まったく。 ワガママな死神だな、と思いながら、そのまま苺は自分の口に運んで体勢を元に戻すと、竜崎が僕のほうを向いたまま固まっていた。 鼻梁が心もち膨らんで、額の辺りは硬直している・・・表情が乏しいから判りにくいが、明らかに竜崎はムッとしていた。 ・・・もしかして苺は最後の楽しみ、だったのか? さすがに気まずい。口の中にある苺の甘酸っぱさが、急に苦いものに変わったような気がして、まだ口をつけていなかったエクレアを謝罪として渡す。 竜崎は黙って受取ってくれたけれど、態度からは落胆が滲み出ていて・・・意外にも可愛らしいところがあると知った瞬間だった。 まだ、あの時のことを根に持っていたのか? 「僕はチョコレートケーキがあるから」 感情を表に出さないように気をつけながら言い、麦茶を出してやると竜崎は意外そうに小首をかしげた。 「苺、お好きなのではなかったのですか?」 竜崎の表情や語調からは、嫌味も嘲りも感じられなかった。純粋に好意で用意したということなのだろうか。 「あの時は悪かった。もう盗ったりしないから安心してくれ・・・・・なに、してるんだ?」 ふと気づくと、竜崎が麦茶に何か粉末のようなものを溶かしていた。 「パウダーシュガーですよ。ライト君も使いますか?」 って、差し出されても。 「色は珈琲に似ていても、これは麦茶なんだけど?」 「ええ。麦茶に砂糖です。ライト君のお宅では入れる習慣がありませんか?」 甘党にもほどがあるぞ、竜崎! どうして当然のように砂糖を持ち歩いているんだ。それに、普通は麦茶ってのは、そのままで飲むだろう? いや、夏バテ防止として塩を入れる家庭があるというのは耳にしたことがあるんだが。砂糖は・・・ 「やはり麦茶には砂糖ですね。ミルクを入れるよりも私はこっちのほうがいい」 麦茶にミルク!? 考えただけで眩暈を起こしそうになっている僕に、リュークまでもが追い討ちをかけてくる。 『ライト、人間のくせに知らないのか? 俺は味を知らないが、麦茶に砂糖や塩や牛乳やキナコを入れる人間って、結構いるんだぜ』 ・・・死神は、少なくともリュークは今まで僕に嘘をついたことはない。と、いうことは事実なのか。カルチャーショックだ。 というか、僕が知らない人間界のことをリュークが知っているということも驚きだ。 狼狽している僕には構わず、竜崎が幸せそうにケーキを口にし始めて 「食べないんですか? とても美味しいケーキですよ」 今度こそ苺まで堪能してから問う。 「ん。欲しいなら食べていいよ。苺タルトもチョコレートケーキも」 「では苺タルトは遠慮なく。でも2人で食べたほうが『友達』って感じがしていいので、ライト君も食べて下さい」 早速、苺タルトを口に運び出した竜崎に肩をすくめ、僕は何も入っていない普通の麦茶を一口、飲んでからチョコレートケーキを食べた。 ほろ苦く甘いケーキは、受けたショックを和らげてくれるような美味しさだった。 【終】 |
| 戻る |
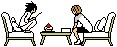 |