8)深潭に咲き誇る藪椿
―――『貴方の手で…どうか、僕の全てを奪ってください』
潤んだ瞳を揺らめかせて、僕に強請る姿はまるで娼婦のように艶かしくて僕の心を掴んで放さなかった。
埃が舞い上がる薄暗いお堂の中で、組み敷いた真史の身体がボンヤリと白く浮かび上がるのが見えた。
子供のような身体だと思っていたのだが、脱がせてみると意外に筋肉質でしっかり とした体つきだった。
彼の身体は薄暗いこの中で蛍烏賊のようにボンヤリと光っているようだ。
僕はその強烈な青白い光に誘われるように真史の首筋に唇を寄せ、強く吸い付き噛みついた。
「…っつ、…うっ…」
微かに真史の口から痛みを訴える声が洩れた。
僕はその声に弾かれたように真史を窺った。
しかし、真史は顔を片手で隠したままでその表情が苦痛なのかどうか窺い知る事は出来なかった。
真史の唾液に塗れた僕の指を真史の後腔にゆっくりと差し入れる。
堅く閉じたそこへやや力を入れて推し進めた。
「…ん……っ…」
身体をピクリと震わせて我慢した真史のくぐもった声が洩れ聞こえた。
「声を聞かせて?」
僕はときめきにも似た心臓の音を聞きながら、腹の上に撒き散らされた二人分の精液を掬い取っては、彼の後腔になでつけるようにして指の出し入れをしつづけた。
彼は時折、苦しそうな声で喘ぎながらも、拒否することなく僕を受け入れようとし
ているように見えた。真史の後腔が淫乱な声を上げ始め、指が1本ではなくもっと
太いものを欲しがるように、ヒクヒクと動き始めた。僕自身は一度達したにもかかわらず、真史の誘いを受け取るかのように、大きく膨らみそして動き始め、今では固
く欲望を滾らせていた。
僕は彼の後腔に指を出し入れするだけで、それ以上は何もしなかった。
ただ、雨のようにキスを降らし、固く尖った乳首を触り、自身の腹で彼の雄を擦った。真史の声が次第に大きく漏れ聞こえてくると、僕は優越感に浸り、次第に我を忘れるようになればいいのにと囁いた。
普段、禁欲的に見える真史が、欲に流され自分を欲しがる様は、僕を有頂天にさせた。僕は調子にのって彼を弄る様に刺激を与えては引いてを繰り返し、決して彼の望むものを与えようとはしなかった。
恨めしげな彼の瞳は揺らめいて僕に縋りつくように見えた。
彼の体が次第に揺れ始め、僕を欲しがるよに弄る手が荒々しく動きはじめた。
―――『…そうだ。もっと貪欲に僕を求めろ。そして、僕だけを望んで』
僕はもう一度、先ほどとは違う場所に又、唇を寄せて吸い付いた。
しかし、今度は真史の口から先ほどの声は聞こえなかった。
但し、今度はそれとは 違う声色で真史の口から声が聞こえた。
それは明らかに『欲』を含んだものだった。
「あぁ…っぁ…」
僕は口角を上げて笑い、その声色をもっと聞きたくて僕は彼の身体に際限なく吸い付いた。
僕は自然と洩れる微笑を御する事もせず、真史の身体につけた新たな痣に目をやると、その痣が何かの形に似ていると思った。
僕は眼前の真史をしばし忘れ思案に耽った。
―――『アレは…何と言う花だったろうか?』
冬でも枯れない青々とした葉を繁らせて、燃えるような赤色の花びらを凛とした面持ちで咲くあの花だ。白い雪の中から燃えるような花びらを覗かせて、人を誘うあの花だ。
僕は青白い真史の胸を撫でまわしながら、薄っすらと浮かび上がる赤い痣を見つめていた。
ふと、真史が身じろぐ気配を感じ、痣から目を背け真史の顔を見ると不思議そうな面持ちで僕を見つめていた。
「……」
真史は乱れた姿とは不釣合いな目線で僕を見つめて何事か喋ろうとしているようだ ったが、結局何も言わずに口をつぐんでしまった。
「…何か、言いたいの?」
僕はさも、興味などないといった口調で問いかけたが、彼の口から発せられようとした言動に不安を感じ、動揺していた。
「…いえ…何も…」
やや乱れた呼吸で目を伏せてしまった真史を見ていると収まりかけた欲望が又ぶり返すのを感じ、薄いピンク色の真史の乳首にむしゃぶりついた。驚いたように身体を強張らせる真史だったが、今度は自分の顔を隠さず、その両手で恐々と僕の頭を掻き抱いた。
僕は少し真史の行動に驚いたが、さも何事も無かったようにそのまま歯を立てて甘噛みしたり、強く吸い付いたり、僕の舌の奥のほうからねっとりと舐め上げたりして愛撫を続けた。勿論、指の出し入れだけは止めることはせずに、浅く出し入れを繰り返していた。彼の欲求が己を超え始めたのだろうか、自分の尻をやや持ち上げてゆらゆらとゆれ始め、自分の奥にある柔らかい部分に導くように誘ってきた。
彼の身体が揺れ始めると、僕の指を僕の意思で動かさなくても、彼の身体が纏わりつくように動き、自らの意思で僕の指を更なる奥へと引き込むように動き始めた。
「…い…ぃ…。……ぁ…ッ」
短い声にならない音を吐き出す真史の背中が弓なりに反った。
「はぁ…あっ…ぁ…ッ」
喘ぎ声は色を含んで艶やかだったが、どこか不安気に聞こえた。
そうやって暫くの間、僕は真史の胸を傍若無人に嘗め尽くしていたが、肝心な、彼の望む何かを与えようとはしなかった。ただひたすら思い出さない花のような痣を
史の身体に付けていった。真史の表情は困ったように僕を見つめるだけで何も話そうとはしなかった。そんな真史の心を僕は見透かしたように笑い、彼に言った。
「して欲しいことがあるの?」
意地悪い言葉だと真史は思っただろうか?
彼の望みを知っているのに、業と焦らすように聞く僕を真史は困った顔をして微笑んだ。何か言葉を話そうとしている真史だったが、結局、言葉でなく吐き出したのは色を含んだ吐息だった。そして、彼の唇は彼の気持を代弁することはなかったが、彼の大きな黒い瞳は僕に何かを告げるように揺れていた
。
**********************
僕は、人から好かれた記憶がない。
性格が悪いのはわかりっきた答えなので、今更だ。
放埓に振る舞い、自分を理解しない人々を蔑んで、見下して、傍若無人に振舞うババリアの狂王のように僕は孤独を生きてきた。世間を呪い、当てもなく広がる社会に暗く沈んでいたのだ。
自分を理解して欲しくて、欲しくて堪らないクセに、僕は無意味な矜持の為に何も
かも無くしていた。
そんな諦めにも似た世界の中に、強く輝き放つ黒い瞳の真史に出逢った。これは…偶然、それとも必然だろうか?
僕はどうしても真史が欲しかった。
僕の周りにいなかった人物。
僕を惹きつけてやまないその存在を。
そこに現れた暖かい光を僕は見逃さす、きっとこの手に収める為に僕は何でもするだろう。
この暗い世界から這い出すために。
真史のためならこの暗い世界と手を切ろう。
彼が僕を望むなら。
だからどうか僕を欲してくれ。
君が僕を望んでくれるなら、僕は何もいらない。
***********************
僕は彼の中から指を引き抜き、足を広げ尻を持ち上げた。
更に、ゆっくりとした調子で彼に覆いかぶさり、注意深く彼を侵食していった。真史は驚いて目を大きく見開いて僕から顔を逸らした。顔は一層赤く上気しており、それはこれからおこりうる行為を想像してなのか、それとも心を見抜かれたゆえの恥ずかしさなのか判断はつかかった。
「…ふ…っ……んっ…」
清純そうな顔を真っ赤に染めているのに、眉間に寄せた苦痛の皺は、
この場に相応 しい艶かしさだった。
僕は身体を更に真史の中へ進めながら言った。
「…真史の身体に…花が咲いているようだ」
僕は緩い動作で上下に動き始め、言葉を聞かせるわけでもなくそう呟くと、暫くして僕の声が届いたのか僅かに頬を引きつらせて少しだけ閉じかけた瞳を真史は開けた。
「…あぁ……っ」
彼の声は短く、言葉になっていなかった。
「真史に付けた痣が、花のように見えるんだ」
僕は呟くように真史への問いを口にして、先程よりも少し早い動作で真史を揺らしてみた。
「ふっ…んっ…ッ」
半眼の眼差しのまま真史は、僕の腰に手を伸ばして掴んだ。
「赤いね…花が、真史の身体に咲いているんだ。……家の庭にある二本の木に咲く花のようなんだ。…でも名前がね、思い出せない」
そう言って僕は思いっきり、真史を突き上げた。
「ああぁ――っ!…」
真史は目を大きく見開き、嬌声を上げた。
途端に、僕の竿は強く真史によって締め付けられ、そのまま奥へ持っていかれそうな感じがした。僕は真史の奥へ、更にその先へ向かいたくて、彼の左足の膝を抑えて開いていた手を今度は、膝裏に手を掛け、彼の足を高く持ち上げて胸まで引き上げた。そして、ゆっくりと体重を掛けて更に奥へと真史の中に入っていった。
彼の両手は僕の背中に回り、僕を引き寄せるように更に奥へと導いた。
「りょ…凌二…さんのお庭にある…のは……『藪椿』で…」
真史は僕の耳に唇を寄せ、甘い吐息がかかるほど近づくと、途切れ途切れに言葉を喋った。彼の言葉は聞き取りにくかったが、嬌声を出しつづけた真史の声が擦れているせいで、そんな声も甘い囁きに聞こえる自分に苦笑いを漏らした。
―――『あぁ、そういえばそうだな、そんな名前だった』
彼の言葉は意外だった。
独り言のように呟いた話を彼が聞いていたことに。
僕は激しく彼を揺さぶり始めた。
「あっ…ああっ…」
「い、家に来る庭師が、そんなことを言っていたよ。…そう、椿か…」
僕は時々感じられる、電撃のような痺れを、何度かやり過ごしながら、身体を震わして揺さぶられる真史を眺めた。
「…は、い…赤い椿、で……んっ…っ」
「赤い椿が……どうした?」
僕は笑って意地悪く問い返し、真史に口付けをした。
「ううっ…んっ…ッ」
真史は堪えきれないように、顔を振ろうとしたが、僕はそれを許さなかった。
荒い息をつきながら僕を見上げる真史の目がとても綺麗で、僕は魅入られたように眺めた。
そして僕は、彼の中から僕自身を素早く引き抜くと、力の抜けた真史をひっくり返 してうつ伏せにした。
真史の骨ばった背中を前に僕はキスの雨を降らせた。
すると、ぶるりと四肢を震わしたかと思うと次々に真史の背中に赤い痣が現れた。
青白い真史の背中に現れた赤い痣を見て僕は満足げに笑い眺めた。
それはまるで赤く咲き誇る裏庭の椿のようだった。
一通り眺め飽きると、僕は又、彼をひっくり返して仰向けにした。
そして、今度も背中と同じ様にキスをして胸に、腕に、腹に赤い椿の花を咲かせた。
真史は僕のすることを嫌がりもせず、ただじっと動かずに僕の一挙一動を窺っていた。その大きく見開いた真っ黒な目が、キラキラを輝いて赤く色づいた花を全身に纏い、しな垂れる身体を横たえている真史の姿は美しかった。
僕は再度、彼の足を持ち上げると、自然に尻を持ち上げる格好となり、
まだ僕の形を残したままの真史の後腔が眼前に晒された。
そこは妖しげに息づき、僕が放った熱の残りが白い糸を引いて流れ落ちる瞬間だった。いまだ疲れを知らない僕の熱は彼の後腔を見ると又、ぶり返してしまい彼に覆いかぶさるように差し入れた。
「はぁっ……はぁ…ッ」
真史は声を荒げて、のど仏を突き出し背中を反らせると中を進む僕を強く締め上げた。彼の中は蕩ける様に熱く、僕の形をそのままかたどるようにピッタリと合わさた。僕も彼も同じように荒い息遣いをしながら見詰め合った。
僕の下で喘ぐ真史は僕の家の庭のようだ。
それは落ちた椿の花で真っ赤に染まった庭であり、白い雪の中に咲き誇る椿自身だった。
家にいる時は何も感じなかったこの感覚は、真史を手中に出来た今、僕が最も感じた感覚だった。
まるで、天国にいるようだ。
君の吐息が僕を惑わせる。
君の瞳が僕を射抜く。
君が僕の腕を掴むと、僕は理性をなくして自制がきかなくなる。
君が僕のものになるのなら、僕を愛してくれるなら僕は何でもしよう。
僕の持っている全てを奪い去って、真史の傍へ攫って行ってくれ。
真史だけが住んでいる楽園に僕を連れて行ってくれ。
君が僕に触れるたびに僕は浮かれた気分になるんだ。
どうか、僕だけを連れって行って欲しい。
僕は激しく真史を揺らして打ちつけ、パンパンと肉がぶつかり合う高い音が古いお堂に響き渡る。
白く輝く光が僕達二人を一瞬、覆い尽くしたような感覚が僕の全身を駆け巡った。真史のくぐもった嬌声と同時に。
僕はだらしなく真史の身体の上に覆いかぶさり、肩で荒い息をしていた。
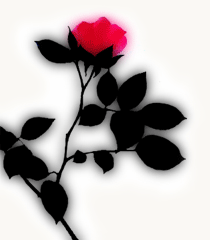 真史は僕の背中に両手を回し、強く抱きしめてくれていた。
真史は僕の背中に両手を回し、強く抱きしめてくれていた。
自分のけだるい身体を、幾分落ち着いたと思われる真史の胸に預けながら満たされた気分をしみじみと味わった。
これから、僕は真史の事を「僕の椿」と呼んでみようかと考えた。
彼の身体に咲き誇るあの花は、僕のためにだけに咲く花なのだ。
誰も知らない美しい花。
真史の身体に咲く椿は僕しか知らない秘密だと思うと、僕は優越感を覚え、
幻想に浸った。
―――『あぁ、僕の、僕だけの赤い椿』