15) バンド活動と文化祭
いつも逃げてばかりだと思う。
そして、逃げて身を隠す場所は画室しかなかった。人気のなかった部屋は夏なのに薄ら寒い気がした。電気のスイッチを捜し、押すと白熱灯の眩しい光が眼の前に広がった。僕は自身に課せた『一日一回以上のデッサンをすること』を行なうために、椅子に座り絵の具で汚れたイーゼルの前にいた。描きかけのスケッチブックを眺めながら木炭握り締め、目の前にある対象物を見ていた。木炭の芯が画用紙にあたるたびに、カスカスと心地よい掠れた音が耳をつき、先程まで動揺し、疲れていた自分が嘘のように平和で快適なものへ変化していった。頭の中で鳴り響いていた不快で猥雑なものがなくなり、ただひたすら目の前の物を見つめ、描くという作業に没頭していった。どれほどの時間が経っただろうか? 時間は僕の傍を擦り抜けるように駆け抜けていた。
そんな時、右肩の辺りに生暖かい温もりを感じた。
「暑くないのか? エアコンつけても……」
耳の傍で聞こえる声に覚えがあったが、僕は酷く驚き、振り返った。
琳は戸惑いを隠せない様な声をだしていた。
「……なんだよ?! 俺がなんかしたか?」
「いや、違う。ビックリしただけ」
「そう……何? それ、文化祭用?」彼が耳元近くで囁きかけた。
僕は早く鳴り響く鼓動を意識しながら、答えた。
「一日一回は、スケッチブックに向かうって決めたんだ。……才能ない分、努力でカバーしようって考えたんだけど……」
僕は些か自称気味に笑って見せた。
「……そんな風に考えてたのか? 俺、お前の絵……好きだし、上手いって思うよ。
ど素人の俺がこんな事言ったって、気休めにしかなんないけど、いいと思う……うん、絶対」そう言って彼は僕の絵を見ながら頷いていた様に思う。僕は今なら、彼を直視することが出来るのではないかという気がして、彼の眼を見ながら笑いかけた。
「ありがとう、そんなこと言ってくれるの琳だけだよ」
彼は僕が笑いかけた事が意外だったらしく、手で口元を押さえながら、向こうを向いてしまい『この部屋、暑いよな? エアコンかけていい?』と言うと、僕の返事も待たずサイドテーブルの上にあったリモコンの山からエアコン用のものを選び出し、ピッピッとボタンを操作した。
琳は僕の傍から離れると、彼は板ばりの床に寝そべり、散らかっていたクッションを集め、足に一つ、頭の方に二つとり、
自分の居心地のいい場所を探しているようだった。
練習の為のスケッチを終え、文化祭用に書いていた油絵の続きをしようと思い、道具やら材料などを揃えだした。
テレピン油の独特の匂いが鼻をついた。パレットは使い差しの色でいっぱいになってもおり、使わなくなった色を見つけては、パレットナイフで削っていた。ギシギシと絵の具を削る音が一種の音楽のように聞こえた。
琳の方といえば、何やら寝そべりながらゴソゴソとA4サイズ位いの紙束をメモを見ては手を動かしているので『変な姿勢でものを見ていると眼が悪くなるよ』と、注意した。
「眼鏡かけてるから、へいき、平気!」
(ったく、そんな問題じゃないだろ?)
彼はこちらを振り返りもせず、紙束を見ながらボールペンで書き込みをしているところだった。
(あぁ、紙束は譜面の束だったのか)
彼には効き目がないと思っていたが、
「せめて、手元を明るくしたらどうだい?」と、辛抱強く言ってみた。
「……う〜ん、そうだな」
と言って、やおら立ち上がりスピーカー近くに置いてあった、スタンドを取りに行った。
ふと、今まで気が付かなかった事が急に頭を掠めた。
深く胸に沈むようなサックスの音が聞こえだし、誰かを探しているような歌声が流れてきた。彼がステレオのスイッチを押していたことすらもわからなかったが、歌も流れていたこともわからなかった。
僕はこの曲が好きだった。何故なら僕の好きな色を連想させるからだ。光るような青、暗黒のなかにある暗い青。僕は嬉しくなって彼に言った。
「この曲“ラウンド・ミッドナイト”だろ? ……良い曲だね」
「そうだよ……いい曲だろ?」静にかに笑って、ボリュームを上げた。
「うん」と返事をし、僕も笑った。
自分に重く伸し掛かっていたものが、少しは取れた様な気がした。自己中心的ではあるが、それでいいのかもしれないと思った。琳の軟らかい物腰はこちらが見ているととても心地よくて、一人でニヤニヤしながらスケッチを楽しんでいた。
この時がもっと永く続くようにと、和で穏やかな日々が崩れ去らない様にと、僕はひそかに神に祈った。
彼は心地よい曲を大人しく聞いているものだと思っていたのだが、やおら、立ち上がりステレオのある場所に行き、近くのテープの山に手を差込みガチャガチャと探し物をして、雪崩れる様にそこらかしこを、CDとテープでちらかしていった。
僕はやっとわかったような気がした。テープの音を譜面でチェックしているのだ。
「……琳が歌う曲のチェック? それ、宇海さんの新曲?」
彼は曖昧な返事をし、ついには、デッキにテープを入れたり、音を鳴らしてみたり、ガチャガチャとテープを止めたり、巻き戻したり、書き込みをしたりで、真摯な表情をしている彼がカッコよく見えた。結局のところ、彼のそんな姿を見られるだけで幸せを感じてしまうのだ。床に寝そべりながら、クッションを抱えるようして、紙束とニラメッコ状態で、考え込んでいる姿は実に絵になる。
彼はCDプレーヤーにCDをセットし、Wのカセットデッキにもテープを装備させていた。リモコンでレコードを切った。部屋は突然停電にでもなったように、音が消えた。ピッピッとリモコンを操作する小さな音が聞こえ、音がCDプレーヤーから流れ出したが、それは先程とは似ても似つかぬ音の氾濫だった。
流れてくる音楽は、静かで、心地よいとは思わないが、妙にドキドキする、声に艶のあるヴォーカルだった。(僕は彼が聞いている曲以外はわからないし、流行りの曲などは全くと言っていい程、知らなかった)
「なぁ、この曲だけどさ、どう思う?」 と、聞いてきた。
「う〜ん、エロチックな声だと思うけど、誰が、歌ってるの?」
彼の方に向かって足を組み、筆とパレットを持ちながら逆に彼に尋ねたが、答えが意外だったらしく、腹這いになっていた体勢を仰向けにしながら、僕を見た。
「エロい、って思う?」
「……思う、ちょっと官能的で、中性的、音を伸ばすときに微かにビブラートがかかる歌い方をするんだな。無機質な音とは対照的に肉感的な声だ。……誰だろう?」
「……マーティン・ゴアって人が歌ってるけど、曲はカバーだよ。有名な曲じゃないけど、知っている人は知っているってやつだな。6曲入りのミニアルバムだけど、全てがカバーで、俺も原曲は一曲しかしらない」
「ふ〜ん、曲名は?」
「この曲? “Never Turn Your Back On Mother
Earth”この曲の原曲はスパークスっていう兄弟二人組のバンドなんだけど、結構気にいってるんだ。……けっこう、いけるだろ?」
彼は僕の言った質問に答えず、突然、紙束を眺めては、忙しくボールペンを動かしだした。
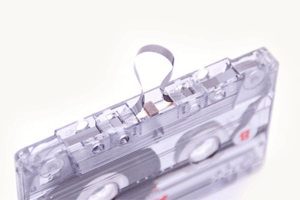
「そのテープにはいってる曲は、みんなそのバンドの曲なの?」
「いや、色々だけど……マーティンはバンドのヴォーカルじゃないよ。彼がバンドとは別にソロとしてカバーのみのアルバムをだしたんだ。バンドのアルバムの時には彼の歌う曲が2曲ぐらいはいるけど、まぁ、彼が作詞作曲してるから、彼が歌っても間違いじゃないわな」
「その曲ばかり、やけに聞き返しているけど……気に入ってる?」
「好きな曲だから、気にいってるもなにもないけど、歌うとなると別の話だよ。どうも、性に合わなくてね、苦手みたいだ」
琳は丸みを帯びた縁なし眼鏡を上目遣いに僕を見て、笑いかけた。
「好きなのに、苦手って事?」
「う〜ん、言いにくいなぁ。でも、どっちの曲が気に入ってるかって言われたら、スパークスの方って言えるな。だから、この曲をマーティンがやった時も『なかなかやるじゃないか』って思ったわけ。そんな風に思ってるとね、頭の中で考えすぎちゃって、歌えなくなるんだ」
「……歌えなくなる?」
「歌うとね、俺の歌い方じゃなくなるんだ。物まねしてるみたいな感じがして、しょうがないんだ。……まぁ、自分の為に存在している曲じゃないからね、仕方がない事だけど。俺だけの解釈だけど、カバーってのは、最初に創造したものへの愛着と感謝の捧げものなんだと思うんだ。だから最初に造り出したものの、もんだからさそれ以上に歌えたり、演奏出来たりするのじゃなく、公開ラブレターの様なものだ、とね。……たまに、それ以上によかったりする奴がいるんだけど」
「琳だって好きなんだから“公開ラブレター”すればいいじゃない?」
「まぁねぇ」
「バンドの曲ってさ、全曲オリジナルじゃなかったっけ? アンコール用?」
彼は“ザーク”と呼ばれるバンドのヴォーカルをしていて、メンバーは全部で5人。宇海 了ことラルフはドイツ人の母をもつハーフで、バンドのリーダーであり、ベーシストである。柚木 津名は琳と中学生の頃からの友達で、リードギターを担当している。探未 新は津名とは同級生でキーボードを担当し、ラルフの古くからの知り合いで、親友でもある辻嶋 新一がドラムを担当している。
ラルフと辻嶋は“エイダ”と呼ばれる伝説のセミプロバンドの中心人物だったが、突然“エイダ”が解散しバンド活動を止めていた。
琳もあまり詳しい事は知らないらしい。
そんなラルフと辻嶋が“ザーク”を結成しバンド活動を再開した理由はわからない。“エイダ”解散の理由は巷で噂された、内部分裂説が一番の定説となっているが、メンバーの一人の自殺が原因とする見方もあるらしい。その後のメンバーの動向が注目されていたが、メンバー全員が姿を消してしまい“エイダ”というバンド名のみが伝説と化していった。
そんな噂の中心人物が、琳と一緒にバンド活動をしているかなどは、全く理解できない事だ。僕は琳からラルフ達との出会いは聞いてはいない。だから、どうやって知り合ったとか、なぜ彼らとバンド活動する様になったかなどは知る由もなかった。ラルフは作詞もするし作曲もする、もちろん楽器も弾くという天才らしいが、プロからの誘いも頻繁にあるが興味をしめそうとしないらしい。
琳は『性格は暗いし、根性はひねくれてるし、けど才能が段違いだ』ラルフの事をこう評した。
僕は彼に質問しながら、続きの絵を描き始めた。
「……いや、ちょっと、練習」
「ふ〜ん、そうなんだ。でも、琳ならいいかも」
「いいかもって?」
「うん、いける。琳が歌うといいかも、ね。なんとなく、似てる感じがするんだ」
「そっかなぁ、俺と似てるかぁ?」
「俺は、あんな風に歌うスタイルじゃないしどちらかというと……」
僕は琳が言い終える前に被さるように言った。
「“チェット・ベッカー”タイプだよ」
彼は少し驚いたように、
「……あんな、声じゃないよ」
『図星かな』と思ったが、
「歌い方だよ。だって、念仏を唱えてるみたいにボソボソ歌ってる感じだから」
「ボソボソねぇ、”チェット”というよりも、“モリッシー”って言ってほしかったな」
「……同じだよ」
「ほぉ、そんな事を言う奴には、お仕置として、毎日耳元で“ブリトニー”を歌ってやる! しかもフリ付きで」
「……あいがたいねぇ、熟睡できるよ、それじゃぁ」
「一度寝ると、二度と起きれないかも……」そう言って、得意気な表情を浮かべて、笑っていた。
僕も笑いながら「練習って……文化祭の舞台で演奏す為?」と、聞いた。
「俺が、か?」考え深げな表情を浮かべる琳を見ながら驚いた。
「去年の文化祭の時、バンド演奏しないか? って誘われてなかったっけ? 結局、執行部の方が忙しいって、出なかったと思うけど……じゃなかった?」
「……う〜ん、そんな事もあった様な気がするな。今年も多分、執行部の方で忙しいと思うが、あ〜でも、クラスで劇をしようとか言っるからそっちにでるかもな」
「クラス劇に、琳がぁ? ……うそぉ〜」
「……なんだよ、その言い方!俺が劇に出ちゃいけないってか?」
「いや、そう言うわけじゃ……珍しいなぁって思っただけだよ」
「……そうかぁ、俺が出るって珍しい?」
「違う! 団体で行動っていうのが琳の行動パターンだよ、似合わないだろ? 琳が舞台にでるっていったら、一騒動起こりそうだと思ったんだよ……あっ、なんか考えただけで悪寒がするぅ。執行部にオハチがまわってきそうだ」
「……お前、演題聞いたらもっとビックリすると思うぞ」
わくわくするような話でもないのに、僕の心臓が早くなった。
「琳の話は心臓に悪いから嫌だなぁ。もう、聞くのよすよ」
「なぁ〜にいってんだかぁ、途中で引き返すのは反則だそ! 突っ込むんだったら、最後までしろよ、男だろ?!」
「……下品〜ん、聞きたくないよ。又、“変なもの”なんだろ?」
「いいや、ファンタジーだ。“サンドリヨン”だよ」
(“サンドリヨン”ってなんだろ?)
僕は彼の言った言葉を知らなかった。
「お前、知らないの、映画見たことない?」琳が不思議そうに僕に聞いた。
「……知らないと、思う。多分」
「〜んなことないと思うぞ。だったら“シンデレラ”っていったらわかるか?」
「えっ?」
「“シンデレラ”って、家族に虐められて、そんでもって魔女の知り合いができて、ガラスの靴をもらって舞踏会にガラスの馬車で行くっていう、やつ?」
「……う〜ん、間違ってはないが、まぁそんなもんだ」
「……で、琳はやっぱり王子様かぁ。似合うだろうなぁ、あ〜でも“警備”が必要?」
僕は素直な気持ちで、そう言ってみた。
琳はバツが悪そうに、咳払いをしてから、
「ちょっと違ってる」
「違う、何が???」
「ん〜なあぁ、俺が出る劇なんだから普通だと思う? フツ〜だったら、出ねぇよ」
「????」
「……王子様はバスケット部の勝山、すぐ死ぬお父様役は、柔道部の手塚。継母役は、サッカー部の友部。3姉妹はバレー部の三高で、高島、高田、高村の三人。そして、主役のシンデレラ役が、俺」
「……」(あ〜ぁ、やっぱり聞くんじゃなかった)
「……どうだ?」
「似合い過ぎて恐い」
「いゃ〜、俺もそう思うよ」
琳は『最高だ!』ともいいたげに、アハハハと、大きな声で笑っていた。
「バンド演奏の方がよかぁないか? …柔道部の手塚なんて、酷すぎるぞ!」
「ひっど〜いぃ事、平気で言うのねぇ、手塚君にいいつけてやるからぁ! そしたらあなたなんか腕菱固めで一本負けよぉ」
「……内股払いで充分だよ」
「でも何で、去年のバンドの件がでたんだ?」と、訝しんだ琳だった。
「さぁ、でも確かに聞いたよ。琳がバンドに出るからって、クラスの中じゃもちきりだったもん」
「お前のクラスで噂になってた?」
「うん、他のクラスでもだよ」
「……なんで、他のクラスの噂まで知ってんだよっ?」
「なに言ってんだよ? 高橋から聞いたの! 一年の時は別だったもん。それに知らない子から『ほんとに出るんですか?』て聞いてきたんだよ。その子デジカメ買うって言ってたしぃ」
「……デジカメってなぁ……」
「デジカメなんてどうでもいいけど、結構話題になってたんじゃない? 皆、琳がバンドにいること、知ってたのかな?」
「〜んな事はない。俺がバンド活動してる事を知っているのは、俺を含めて3人だけだ。…お前に、高橋だけ。学校に知られるのは得策じゃないからな。あ〜とっ、佐伯もいたな」と、言った。
琳はバンド活動を学校の方には知られない様に気を使っている。まぁ、学校の人種からして、彼が立ち寄りそうなところへは、行くような人たちではないので、バレる心配はしてはいなかったが、彼がこの事を秘密にしている理由は知らなかった。彼は僕が、その理由を僕が知りたがった様に思ったのか、言い訳がましく答えてくれた。
「成績優秀、品があって見栄えも良い、おまけに執行部の幹部候補生で、校内一の有名人が、きな臭い如何わしいライブハウスに出入りしているってわかったら、イメージ壊れるじゃん?」
「はぁ〜、イメージねぇ。でも、あの時どうしてバンドの事が話題になったんだろう?」
「……さぁな、俺も詳しくは知らない。……知ってる奴はいたのかもしれんけどね」
「ヤバイ?」
「いや、あれからその話はでてないし、今度の催し物の事で、そんな話がでたことも忘れるだろうさ」
「……相殺効果をマジで狙っているとしたら、君も食えない奴だな」
「Muchas Gracias!」
僕は『ふ〜っ』と大きなため息をついてみせ、首を横に振るった。
「ところで、お前の方はどうなんだ?」
「僕の方? ってクラスはどうだかな? 飲食関係にしてくれたらいいのになぁ。楽だって三森が言ってたし……。でも、さぁ……なんだかさぁ変な案もでていて、『コスプレ喫茶』にしようと言った奴もいたんだよ?」
「なんだそれ? ……全員、女装している喫茶店って事か?」
「いや〜ちょっと違うな。マンガやゲームにでてくるキャラクターと同じ格好をするんだよ。手作りで衣装も同じやつを作ってさ。例えば“クレヨンしんちゃん”のしんちゃんのカッコしたりとか……」
「お前のクラスの方が、一枚上手だよ! 学校始まって以来の珍事だよな?」
「……それが、困るんだよなぁ。こんな企画が通るとは思ってるのかい? 休み明けに、それぞれの案を提出した奴が、企画書を引っさげて演説会をすることになったんだけど、司会なんかしたくないよ」
「堅物の野郎ばかりだと思っていたけど、なかなかどうして、やるじゃん?」
「……やってくれなくてもいいよ。その、コスプレ企画にきまったら、その企画書の提出係は僕だよ! ……担任より、生指の磐田に何言われるか、たまったもんじゃないよ」
僕は休み明けに起こりうる嫌な問題を思いだし、げんなりした。